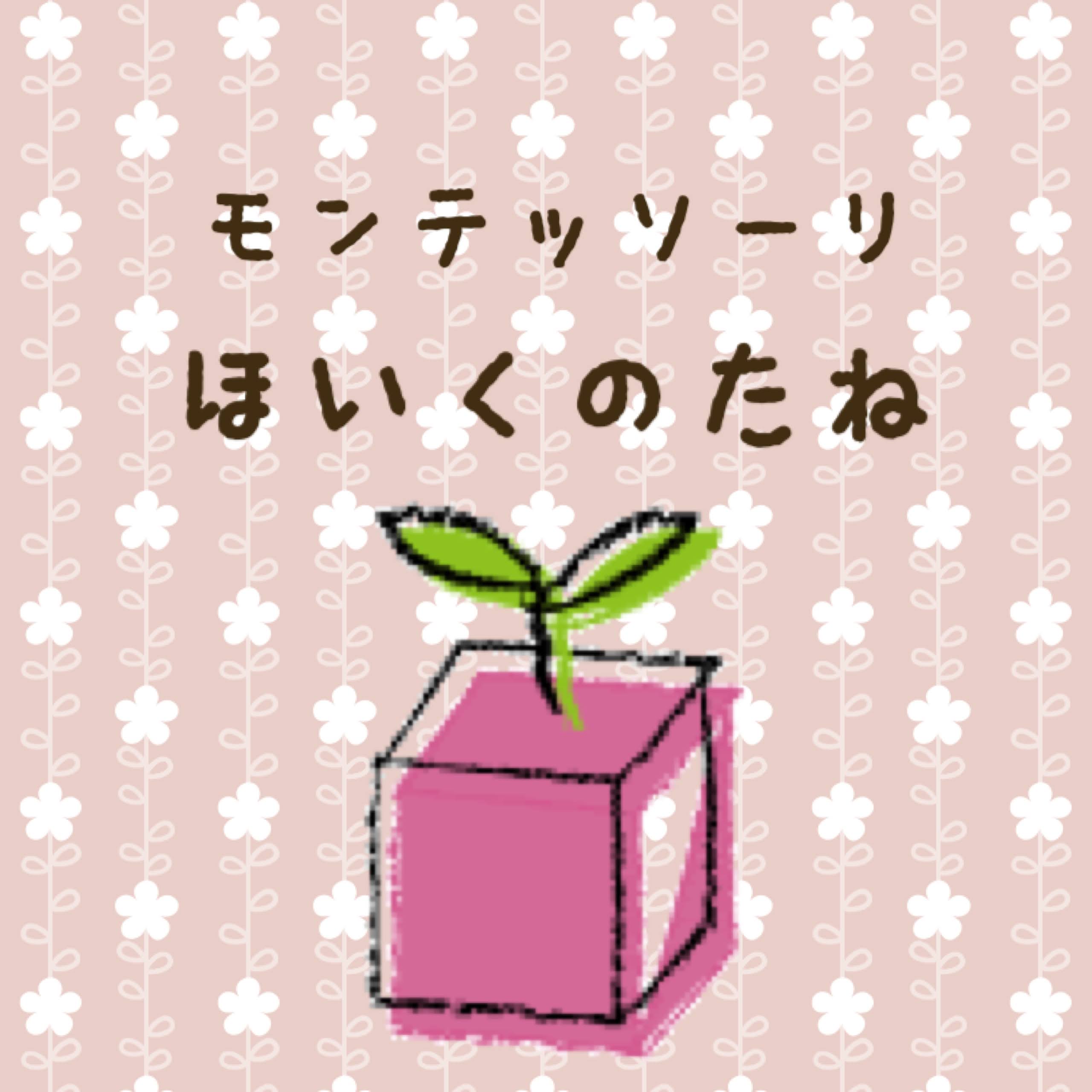モンテッソーリ教育とは
“モンテッソーリ教育”という言葉は知っていても、実際どんなものなのかご存知でない方も多いのではないでしょうか。
モンテッソーリ教育とは、イタリア初の女性医師マリア・モンテッソーリという方が考案した教育法です。その名前をとって、“モンテッソーリ教育”といいます。
最近では、将棋の藤井聡太さんが幼児期に受けていたことで日本でも注目を集めている教育法の一つです。その歴史は長く、最初にモンテッソーリ教育を行う施設「子どもの家」ができたのが1907年(明治40年)で、116年前になります。現在でも、140ヶ国以上の国々で実践されている世界的な教育法です。
日本では、モンテッソーリ教育を早期教育や英才教育、お受験などのイメージを持たれる方も多いようですが、決して特別な目的で行う教育ではありません。
どんな子どもにとっても魅力的で、どんな大人にとっても「知っててよかった♪」と思える考え方やアイデアがいっぱい!
また、保育所保育指針改定から求められている「子ども主体の保育」、よく耳にするようになった「アクティブラーニング」を実践するために役立つヒントもたくさんくれます。

モンテッソーリ教育の始まり
モンテッソーリ教育の始まりは、医師であったマリアが、障がいのある子ども達と出会ったことがきっかけとなりました。
ある日、医師の仕事で病院を訪れたマリアは、障がいのある子ども達が集められている部屋の前で足を止めました。見張りをしていた女性に、子ども達について聞くと、その女性は「この子たちは意地汚い。食事の後、床に落ちたパンくずを拾って食べるんだから」と、とても嫌そうな表情で話したのです。
それを聞いたマリアは部屋の中を見回しました。部屋の中には、おもちゃや道具など、子どもが遊んだり使ったりするものが何もありません。さらにパンくずを拾う子ども達の様子を観察すると、小さなパンくずを見つけて指先を使って拾う時の子ども達の真剣な姿と興味に向かうエネルギーを発見したのです。
そんな子ども達の姿から「手が使いたいんだ」と感じたマリアは、指先を使って土台から出し入れするような教具(今でいう、「円柱さし」のようなもの)を作り、子ども達に提供してみました。手を使いたい!という欲求を満たされた子ども達は、次第に落ち着いて過ごすようになり、障がいのない子ども達と同じように生活できるようになっていきました。このことがきっかけとなり、マリアはこのアイデアはどんな子どもにとっても良いものに違いないと考え、モンテッソーリ教育として確立していきました。
このお話は、モンテッソーリ教育の始まりとして有名なエピソードです。
「子どもを見る目」で教育が変わる
見張りの女性とマリアは、同じ“パンくずを拾う子どもの姿”を見ていたのに、
その捉え方が大きく異なります。その理由は「子どもを見る目」にあります。
一般的に大人というのは、自分の経験や考えが入ったフィルターを通して、先入観を持って物事を見ることが多くあります。
しかし、マリアは医師であったので、科学的な見方、目の前の出来事を観察し自身の思考や推測に頼るのでなく、事実に基づいて誰が見ても納得できる立場で考える習慣が身についていました。つまり、それまで「子どもとはこういうもの」という先入観で見ていた教育に科学の目を導入したのです。
「子どもを観察をする」「先入観を持たずに子どもを見る」
これが、モンテッソーリ教育を実践するうえで、一番大切な大人の姿勢です。
モンテッソーリ教育の実践とは、手作り教具を作って与えるだけでも、教具の使い方が完璧にわかることでもありません。
『いつでも子どもが出発点』
『子どもが私たちの先生』
大事なのはこの姿勢、この子どもの見方を実践することです。これが「子ども主体」の考え方に繋がります。

モンテッソーリ教育をもっと学びたい方へ
モンテッソーリ教育について、もっと知りたい!もっと学びたい!と思った方は、ぜひ「読んで学べるBlog」から記事をご覧ください♪
https://montessori-hoikunotane.com/blog/
学びの場もご用意しております。
メニューから「オンラインサロン」「保育園・企業」をご覧ください。