日常生活の練習の目的や5分野についてお話してきましたが、今回は実際におしごととして用意する時のポイントをお伝えします。ポイントをおさえた上で、柔軟に工夫を凝らして、子どもたちが“面白い”と思えるおしごとを用意していきましょう!!
日常生活の練習の用具を準備する際におさえるポイント
日常生活の練習で使う道具を「用具」と呼びます。(ちなみに、感覚教育以降で使うものを「教具」と呼ぶことになっています。)用具は、既製品があまり販売されていないので、先生方が自分たちでおしごとに合ったものを探して用意する必要があります。
『日常生活の練習』の用具を用意する時のポイント
①子どもの手や背丈に合ったサイズであること
②包丁やガラスなど、本物であること
③子どもが手を出したくなるような、魅力的な色や形であること
④清潔を保てること
⑤日常生活で使っているもの
⑥国や地域の特性が生かされているものがあってもよい。
⑦用意するセットは多すぎず、少なすぎず
一番大事なのは、①子どもに合うサイズ(大きさ、長さ、重さ)の道具を用意し、子どもの高さに合う場所で行えるようにすることです。3歳以上のクラスでは②本物であることも、意識したいところですね。ガラスや包丁など、雑に扱うと壊れたりケガをしたりするので、慎重に扱う姿勢を身に付けることにも役立ちます。また、一般的な保育の現場では、子どもたちが取り合いにならないように数を用意することを良しとしていますが、モンテッソーリ教育のおしごとに関しては⑦用意するセットは多すぎず少なすぎずということになっています。理由は「待つ」ことも大事にしているから。日常生活の練習の間接目的の一つ“社会性を身に付ける”ことにも繋がります。シール貼りやのり貼り、縫い刺しなど、少し時間のかかるおしごとは、人数に応じて2セット以上用意しても良いですが、基本的には1種類1セットでOKです。
用具を配置する時のポイント
準備した用具は、子どもたちが選びやすいように、自主的に活動できるように配置しましょう。
〔1〕棚を用意する
モンテッソーリ教育の環境は棚が一つの特徴でもあると思います。棚があると、多くの用具を部屋に置くことができ、子どもたちにとっては用具を選びやすく、出し入れもしやすくなります。子どもの背丈に合った棚は、モンテッソーリ教育用の既製品もありますし、ホームセンター等で売っているものでも代用できます。
〔2〕トレイにひとまとめにする
作業をスムーズにスタートするために、そのおしごとに使うものは、トレイにひとまとめにしておきましょう。道具をピックアップする必要があるおしごとは、運ぶ用のトレーを置いておいて、その上に自分で用意して席に運んでいきます。
〔3〕分野ごとにまとめて配置
似たような作業は同じ棚や隣に置きます。例えば、シール貼りとのり貼りは、“貼る”という動きが同じなので、近くに配置します。そうすると、シールを十分にやった子が興味を持って手に取ったりします。
日常生活の練習のおしごとは、シール貼りのシール、のり貼りの色紙やのり、ハサミ切りの紙など、消耗品が必要です。「紙がなくてできない」ということが起きないよう、常に補充しましょう。また、ビーズが足りない、壊れているということがないよう、チェックも欠かさずにお願いします!
日常生活の練習を考える時の視点

日常生活の練習という分野は、その名の通り「日常生活で使う様々な動きを練習する場」です。なので、子どもたちと日常生活を共にする中で「ここ難しそう」とか「大人と同じことをやりたがっているな」などと感じた時、おしごとにするならどうやって用意しようかな?と考えてみてください。子どもたちがくり返し楽しんで練習できるようなものを用意して、“提示”をしてやり方を伝えます。そして練習した動きが日常生活に還元されることが理想の流れ。ぜひ、子どもたちを観察して、おしごとのヒントを見つけてみてくださいね。
☻モンテッソーリ教育導入支援 ご相談ください
モンテッソーリほいくのたねでは、保育施設でのモンテッソーリ教育導入、実践の支援を行っています。新たに導入したい園はもちろん、すでにモンテッソーリ教育を導入している園で、子どもたちの興味に合わせてより良い環境を整えていきたい、実践できる先生を増やしていきたいといった、課題に応じたお手伝いしております。
↓どうぞ、お気軽にご相談ください↓
お問い合わせはこちらからどうぞ!


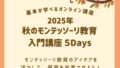
コメント